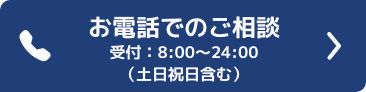株価算定方法に関する判例(TF事件)!
今回解説する裁判例は、譲渡制限株式について、株式価格決定申立がなされた事案です。主に争点となったのは、株式売買価格をどのように算定するかという点でした。
裁判例の本格的な解説へ移る前に、その前提となる予備知識として、株式価格決定申立について確認をしておきます。
そもそも譲渡制限株式は、会社の承認がなければ第三者へ譲渡することができません。譲渡制限株式の株主が、保有する株式を手放したいと考えた場合、まずは会社に対して譲渡承認を請求することになります(会社法136条)。
ここで会社が譲渡承認をしてくれれば良いのですが、問題は承認してもらえない場合です。法律では、会社が株式の譲渡を承認しなかった場合、当該株式は会社(または会社が指定した「指定買取人」)が買い取らなければならないと規定しています(会社法140条)。そうすることで、株主が株式を手放せる権利を保障しているのです。
買い取り価格が決まらない場合は裁判所に決めてもらう
ただ、ここで「株式売買価格」が問題となります。譲渡制限株式には市場価格がないため、売買価格は当事者が協議して決める必要があります(会社法144条1項)。しかし、往々にしてこの協議が決裂してしまうのです。
会社・株主間で株式売買価格の協議が決裂した場合、次の手段は「裁判」です。すなわち、裁判所に対して株式売買価格を決定してもらいます。これが、株式価格決定申立です(会社法144条2項)。
なお、裁判所が株式売買価格を決定するには、「株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない」とされています(会社法144条3項)。
株価算定方法に関する判例:TF事件の概要
それでは、事案の概要について本格的に見ていきましょう。まずは、舞台となった会社のデータを確認します。
会社のデータ
今回の事案では、2つの会社が舞台となります。1社目は、フレキシブルチューブの製造・販売等を行う非上場会社「TF」社です。もう1社は、「TF」社の経営に関する相談・指導等を目的として設立された「TF企画」社です。
「TF」社について
「TF」社は、裁判開始時点(平成25年末)で設立から50年以上の歴史を持っており、業界最大手の同業他社に準ずる規模の事業活動を行っています。
裁判開始時点において、直近数年間の収益は比較的安定している状況にありました。業界全体の出荷額もおおむね安定していたことも加味すると、今後の事業継続が困難になるような事情や、将来における解散が予想されるような事情は認められません。
また「TF」社では、利益の大部分が事業用資産に再投資されていました。
具体的なデータとしては、裁判開始時点における直近3年間(平成22年12月から平成25年11月まで)の数値が挙げられています。これによると、税引前利益の合計は約4.7億円、営業キャッシュ・フローの合計は約1.8億円だったのに対して、同期間における投資キャッシュ・フローの合計はマイナス約7億円となっています。
そのため、株式配当の原資となる非事業用資産が少なく、配当性向も業界内で相対的に低いものとなっていました。
「TF企画」社について
これに対して「TF企画」社は、少なくとも平成22年3月期以降は具体的な事業を行っていませんでした。つまり、「TF」社の株式を保有することだけが目的の「資産管理会社」というわけです。
そのため「TF企画」社の資産は、その大部分が「TF」社株という状況でした。
具体的なデータとしては、平成25年3月期の貸借対照表における保有資産の内訳が挙げられています。これによると、現預金が147万6000円、有価証券が6343万8000円(「TF」社株3万7660株)、預かり保証金が5000万円(「TF」社に対する金銭債権)となっています。(なお、トータルの純資産額については1530万9000円です。)
以上からも、「TF企画」社が具体的な事業を行っていなかったということが分かります。
株式の発行・保有状況
次は、両社が発行する株式について見ていきましょう。
「TF」社の株式について
「TF」社の定款には、株式譲渡に取締役会の承認が必要との定めがありました。すなわち「TF」社の株式は、すべて譲渡制限株式だったということになります。
発行済株式総数は、19万6000株です(裁判開始時点)。そのうち3万7660株は自己株式なので、議決権はありません。
残り16万1120株の議決権株式について、主要な株主は次の通りです。
- 「TF企画」社(持株数3万7660株、議決権比率23.4%)
- G社(持株数2万8060株、議決権比率17.4%)
- 従業員持株会(持株数2万3500株、議決権比率14.6%)
- 「TF」社・「TF企画」社の代表取締役(持株数2万800株、議決権比率12.9%)
なおG社は、「TF」社・「TF企画」社の経営陣を主要な株主(議決権比率55%)とする会社です。
また「TF」社の株主のうち、現経営陣及び友好的な株主の占める割合は、議決権総数の68.3%に及びます。
「TF企画」社の株式について
「TF企画」社の株式も、すべて譲渡制限株式です。
発行済株式総数は、2万3460株です(裁判開始時点)。主要な株主は次の通りです。
- 「TF」社・「TF企画」社の代表取締役(持株数3300株、議決権比率14.1%)
- 「TF」社・「TF企画」社の取締役(持株数3000株、議決権比率12.8%)
- 「TF」社の取締役(持株数3000株、議決権比率12.8%)
- 「TF」社の従業員(持株数3000株、議決権比率12.8%)
なお「TF企画」社は先にも触れたとおり、「TF」社の株式を保有するだけの資産管理会社です。したがって、以上に挙げた「TF企画」社の株主は、「TF」社の株式を間接的に保有しているのと実質的に同じ状況だと言うことができます。
裁判(株価算定方法に関する判例)に至る経緯
また、今回の裁判に至った事実経過は次の通りです。
きっかけは、「TF」社・「TF企画」社の株主であるAが、「TF」社株100株・「TF企画」社株10株を第三者へ譲渡しようとしたことでした。
当該株式はいずれも譲渡制限株式なので、株主Aは「TF」社・「TF企画」社の両社に対して、株式譲渡の承認を請求しました。しかし譲渡は承認されず、代わりに投資ファンドBが買取人に指定されました。
そこで、当事者によって当該株式買取価格が協議されます。しかしこの協議は決裂してしまい、裁判所に対して、株式価格決定申立がなされるに至ったというわけです。
なお、この決定の申立てを行ったのは、投資ファンドBの側でした。そのため、裁判例では投資ファンドBのことを「申立人」、株主Aのことを「利害関係参加人」と表記しています。そこで本稿においても、次項からは裁判例にならって「申立人」「利害関係参加人」との表記を用います。
株価算定方法に関する判例における当事者の主張について
ここからは、申立人(投資ファンドB)及び利害関係参加人(株主A)がどのような主張をしたのか、詳しく見ていきましょう。
「TF」社株の売買価格算定基準について
まずは、「TF」社株の売買価格算定基準についてです。
申立人(投資ファンドB)は、「標準配当還元法」のみによる算定を主張しました。具体的な売買価格としては、1株当たり1958円という金額を提示しました。
これに対して、利害関係参加人(株主A)は、「標準配当還元法」25%、「取引事例法・類似会社比較法」25%、「簿価純資産法」50%の加重平均による算定を主張しました。具体的な売買価格としては、1株当たり1万2996円という金額を提示しました。
「TF企画」社株の売買価格算定基準について
一方、「TF企画」社株の売買価格算定基準については、申立人(投資ファンドB)・利害関係参加人(株主A)ともに「時価純資産法」による算定を主張しました。
もっとも、両者が実際に提示した金額については、かなり開きがありました。申立人(投資ファンドB)側が提示した価格は1株当たり1058円、利害関係参加人(株主A)側が提示した価格は1株当たり2万951円です。
株価算定方法に関する判例における株式売買価格算定基準の全体像について
ここで、当事者の主張に対する理解を深めるための予備知識として、株式売買価格の算定基準について、その全体像を確認しておきましょう。
そもそも、株式売買価格を算定する基準は、①インカムアプローチ、②マーケットアプローチ、③コストアプローチの3種類に分類されます。
それぞれの内容について、簡単に見ていくことにしましょう。
インカムアプローチについて
インカムアプローチとは、会社の事業活動が将来もたらす収益(インカム)を基礎にして、その会社の株価を算定する方法です。
株価算定の基礎になる「収益」をどう考えるかによって、さらに細かく分類されます。
ここでいう収益のことを、「将来において株主にもたらされると予想される配当額」と考えるならば、「配当還元法」と呼ばれる算定基準を用いることになります。なお、今回の事案で当事者の主張に登場した「標準配当還元法」は、この算定基準に該当します。
一方、収益を「将来において予想されるフリー・キャッシュ・フロー(会社の事業活動を通じて生み出され、株主及び債権者に分配し得るキャッシュ・フロー)」と考えるならば、「DCF法」と呼ばれる算定基準を用いることになります。
インカムアプローチの一般的なメリットとしては、会社の将来的な収益力の変化を考慮できるため、今後も事業を続けていく「継続会社」の株価算定に適しているという点が挙げられます。
これに対して、一般的なデメリットとしては、「将来の収益力の予測には困難が伴い、恣意的な算定になるおそれがある」という点が挙げられます。
マーケットアプローチについて
マーケットアプローチとは、類似する会社・事業・取引事例における株価(マーケット)を比較対象として、相対的に株価を算定する方法です。
比較対象として何を用いるかによって、さらに細かく分類されます。
今回の事案で登場した「取引事例法」では、算定対象の会社における過去の株式取引を比較対象として用います。基本的には、最も直近の取引価格を比較対象として株価を算定します。具体的な株価を比較対象とするので客観性が担保される点がメリットとされますが、市場性のない非上場株式の過去の取引価格が比較対象として適切なのかという疑問は残ります。
一方、今回の事案で登場した「類似会社比較法」では、算定対象の会社と類似した上場会社の株価を比較対象として用います。類似会社の選定に際しては、事業内容・事業規模・収益性・成長性など、様々なファクターが考慮されます。類似会社の選定が適切であれば客観的な株価算定が可能となりますが、類似会社が見つからない場合には使いづらい基準だと言えるでしょう。
コストアプローチについて
コストアプローチとは、会社のバランスシート上に記載された純資産額を基礎として、株価を算定する方法です。
バランスシート上の純資産額をそのまま用いる方法は、「簿価純資産法」と呼ばれます。これに対して、今回の事案で登場した「時価純資産法」では、バランスシート上の資産・負債を時価で評価し直したうえで、改めて純資産額を計算し直します。
コストアプローチには、会社の将来の収益力を一切考慮できないという問題点があります。そのため、清算を予定している会社の株価を算定する際には使えますが、今後も事業を継続する会社の株価を算定するには不向きだと言われています。
株価算定基準に関する裁判所(株価算定方法に関する判例)の判断について
以上の予備知識を踏まえて、当事者が主張した株価算定基準に関する裁判所の判断について、詳しく見ていきましょう。
標準配当還元法
申立人(投資ファンドB)が「TF」社株の売買価格算定基準として主張した「標準配当還元法」について、裁判所は肯定的に評価しています。
「TF」社が継続会社である
その理由のひとつは、「TF」社が今後も事業を継続する予定の「継続会社」であるという点にあります。
つまり、特に清算を予定しておらず、将来も収益を上げていくことが予想される「TF」社の株価を算定するには、会社の将来の収益力を考慮できる「標準配当還元法」を用いるのがもっとも適切である、という判断がされているのです。
売買対象となる株式の議決権総数に占める割合がわずかである
もう一つの理由として、本件において売買の対象となっている「TF」社株100株が、議決権総数に対して0.06%という少数株にすぎないという点も挙げられています。
この点、先に触れたように「TF」社においては現経営陣及び友好的な株主が、議決権総数の68.3%もの株式を保有しています。こうした状況下で0.06%の少数株を売買しても、経営権に与える影響は全くないと言えます。
すると、本件の株式売買によって得られる利益は、会社支配権ではなく配当であると考えるのが自然だということになります。
そのため、株式売買価格の決定に際しては、株主に将来もたらされることが予想される配当額を算定の基礎とする「標準配当還元法」を用いるのが適切である、という判断がなされたというわけです。
取引事例法
利害関係参加人(株主A)が「TF」社株の売買価格算定基準として主張した「取引事例法」について、裁判所の評価は否定的です。
株式に市場性がない
その理由は、非上場会社である「TF」社株の取引には市場性がない、という点にあります。つまり、市場性のない株式の売買は個別性・特殊性が強いため、株価算定の指標として用いるだけの客観性を備えていないと判断されたのです。
類似会社比較法
利害関係参加人(株主A)が「TF」社株の売買価格算定基準として主張した「類似会社比較法」についても、裁判所は否定的に評価しています。
類似する上場会社が存在しない
その理由は、「TF」社に類似する上場会社は存在しない、という点にあります。比較対象として適切な上場会社が存在しない以上、「類似会社比較法」は使えないというわけです。
簿価純資産法
利害関係参加人(株主A)が「TF」社株の売買価格算定基準として主張した「簿価純資産法」についても、裁判所は否定的に評価しています。
継続会社を評価するのには向いていない
その理由として挙げられているのは、A社が事業継続を前提とした「継続会社」であるという点です。
つまり、純資産法ではA社の将来における収益力の変化を一切考慮できないため、株価の過大評価になってしまうと判断されているのです。
コストアプローチによる株価算定基準は、継続会社の株価算定に用いるには不適切であるとの考え方が、裁判所によって採用されたと言うことができるでしょう。
時価純資産法
一方「時価純資産法」は、「TF企画」社の株価を算定する基準として、申立人・利害関係参加人のいずれによって主張されています。これに対しては、裁判所も肯定的な評価をしています。
その理由としては、「TF企画」社は「TF」社株の保有のみを目的とする資産管理会社である、という点が挙げられています。
というのも、「TF企画」社は「TF」社株の保有以外に、何の事業も行っていません。そのため、事業による収益を考慮するインカムアプローチによる算定基準は不適切だと考えられます。
先に見たように、「TF企画」社における平成25年3月期の保有資産の内訳は、現預金が147万6000円、有価証券が6343万8000円(「TF」社株3万7660株)、預かり保証金が5000万円(「TF」社に対する金銭債権)となっています。
つまり「TF企画」社の企業価値は、その保有資産の大部分を占める「TF」社株の価値によって決まると考えられるのです。したがって、「TF企画」社の純資産額を株価算定の基礎とするのが最も適切だということになります。
また、「TF企画」社が保有する「TF」社株の価値を算定するに際しては、帳簿上の金額をそのまま使用するのではなく、現在の時価に引き直して評価するのがより正確だと考えられます。そのため、簿価純資産法ではなく「時価純資産法」を用いるべきだと判断されているのです。
裁判所(株価算定方法に関する判例)による売買価格の算定について
最後に、今回の事案で裁判所が株価をどのように算定したのか見ていきましょう。
「TF」社株の売買価格について
「TF」社株の売買価格について、裁判所が適切な算定基準として認定したのは「標準配当還元法」だけです。したがって、標準配当還元法を単独で用いて算定することになりました。
標準配当還元法の計算式
標準配当還元法では、「株式の現在価格=予想配当額×割引率」という計算式を用います。
すなわち、株主が将来受けられる配当の金額をベースとしたうえで、そこに割引率を乗じて現在価値へ引き直すことで、現在の株価を算出するのです。
予想配当額の算出
そこで、まずは予想配当額を求めるところから始めます。予想配当額を求める計算式は、「将来利益×予想配当性向」です。
このうち「将来利益」については、「TF」社の実績値をベースに計算しました。先に触れたように「TF」社の利益は比較的安定しているので、実績値をベースに将来利益を算出することは適切だと言えます。
一方で「予想配当性向」については、業界平均(19.5%)と上場会社平均(33.0%)を併用しました。なお「TF」社自体の配当性向については、相対的に低水準であることを理由に、そのまま用いることは不適切だという判断になっています。
割引率の算出
割引率については、会社が資本により追加的に資金調達をする際に資本拠出者から要求される利率である「株主資本コスト」が採用されました。
また、株主資本コストを求める計算式には、「β×市場リスクプレミアム+無リスク金利」(資本資産評価モデル)が採用されました。
なお、βとは「株式市場全体の利回りに対する個別株式の利回りの連動性の度合いを示す数値」です。もっとも非上場会社である「TF」社の株価には市場性がないため、類似する上場会社のβから推測する方法で算出します。
一方、市場リスクプレミアムについては過去50年の平均値を採用し、無リスク金利については10年国債利回りを採用しました。
最終的に算出した売買価格
以上の計算手順を踏まえて、①業界平均の予想配当性向を用いて算出した株価と、②上場会社平均の予想配当性向を用いて算出した株価をそれぞれ求め、両者の平均値である「1株当たり2195円」という価格を算出しました。
株価算定方法に関する判例における「TF企画」社株の売買価格について
「TF企画」社株の売買価格については、時価純資産法を単独で用いて算出しました。
時価純資産法の計算式
時価純資産法では、「時価純資産額÷発行済株式総数」という計算式で株価を算出します。
そして「TF企画」社の時価純資産額を求める計算式については、「簿価純資産額+「TF」社株式の時価と簿価の差額-税効果影響額」と認定されました。「TF企画」社の純資産の大部分が「TF」社株式であることを考慮して、同株式による含み益を加算する計算式となっています。
「TF」社株式の時価と簿価の差額(含み益)
そこでまず、「TF」社株式の時価と簿価の差額(含み益)について計算します。
「TF」社株式の時価については、裁判所による算定額である「1株当たり2195円」を用います。一方、「TF」社株式の簿価については、貸借対照表上の額面である「1株当たり1684円」を用います。
そして、「TF企画」社が保有する「TF」社株式の数は、前に触れたとおり3万7660株です。
したがって、「TF」社株式の時価と簿価の差額は「2195円×3万7660株-1684円×3万7660株=1924万4260円」と算定されました。
税効果影響額の算出
次に、税効果影響額について計算します。
ここでいう税効果影響額とは、主として法人税の負担を意味します。したがって、まずは「利益剰余金×税率」という計算式が考えられます。
さらに本件の「TF企画」社では、保有する「TF」社株式の含み益への課税についても考慮する必要があります。この点については、「「TF」社株式の時価と簿価との差額×税率」という計算式を使うことになります。
以上の2点を総合して、最終的には「(利益剰余金+「TF」社株式の時価と簿価との差額)×税率」という計算式が用いられました。
このうち利益剰余金については、貸借対照表上の額面である「マイナス815万1000円」を用います。また、「TF」社株式の時価と簿価との差額については、先ほど算出した「1924万4260円」を用います。さらに税率は37.07%とします。
その結果、税効果影響額は「(1924万4260円-815万1000円)×37.07%=411万2642円」と算定されました。
最終的に算出した売買価格
以上の計算結果をもとに、「簿価純資産額+「TF」社株式の時価と簿価の差額-税効果影響額」の計算式によって「TF」社株式の総額を算出します。
そして「簿価純資産額」については、貸借対照表上の額面である「1530万9000円」を用います。
つまり、「TF企画」社株の総額は「1530万9000円+1924万4260円-411万2642円=3044万0618円」と算出されます。
なお「TF企画」社の発行済株式総数は2万3460株です。したがって、「TF企画」社株の1株当たりの株価は「3044万0618円÷2万3460株=1298円」と算出されました。