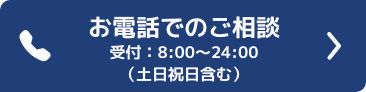株価算定方法に関する判例(テレネット事件)!
株価算定方法に関する判例 テレネット事件の概要
今回扱う株式売買価格決定申立事件の裁判例は、ベンチャー企業「テレネット社」が発行する譲渡制限株式の売買価格が問題となりました。平成19年3月22日に同社の株主が、株式価格決定申立を裁判所に対して行ったのです。
会社のデータ
テレネット社は、デジタルコンテンツの配信事業を営む非上場会社です。設立されたのは平成12年2月8日で、定款には株式の譲渡制限の定めがあります。
同社の売上については、平成15年12月期が約8266万円で、平成19年3月期が約1億1618万円となっています。売上1億円程度の事業規模を保ちながら、上昇方向に推移している状況だったと言えます。
他方で、同社の販管費は減少傾向にありました。平成17年3月期までは1年あたり約5582万円の販管費を計上していましたが、平成18年3月期は約692万円、平成19年3月期は約1672万円と格段に減っています。
つまりテレネット社は設立以降、事業を軌道に乗せながら営業利益を拡大してきた「成長企業」だったと言えるでしょう。
その一方、裁判当時に至るまで、同社が株主に対して配当を行った実績はなく、将来配当を行う予定もありませんでした。
発行株式の状況および裁判(株価算定方法に関する判例)に至る経緯
テレネット社の発行済株式総数は、6000株でした。そして裁判の時点で、同社には2人の株主がいました。一方の株主Aの保有株式数は2400株で、もう一方の株主Bの保有株式数は3600株でした。
そのうち2400株を保有する株主Aが、自身の保有する全株式を第三者に対して譲渡しようと考えました。
もっとも譲渡制限株式は、会社が承認をしなければ第三者に対して譲渡することができません(会社法2条17号)。株主または株式取得者による譲渡承認請求が会社によって否定された場合、当該株式は会社(または会社が指定した買取人)が買い取ることになります(会社法140条)。
そこで株主Aは、テレネット社に対して譲渡承認請求を行いました。しかし同社はこれを承認せず、株主Bを指定買取人とする旨を通知しました。
この場合、株式買取価格は、当事者の協議に任されることになります(会社法144条1項)。しかし、今回の事案ではこの協議が調いませんでした。
そこで、株主Aから裁判所に対して、問題となった2400株について、株式価格決定申立(会社法144条2項)がなされたのです。
なお、本件申立ての裁判例において、株主Aは「申立人」、株主Bは「相手方」と表記されています。ここからは本稿においても、裁判例の表記に従って「申立人」「相手方」と呼ぶこととします。
株価算定方法に関する判例において各当事者が主張した売買価格について
それでは問題となった2400株について、申立人および相手方が主張した売買価格を見ていきましょう。
申立人が主張した売買価格
申立人は「収益還元法」「取引事例法」「類似会社比較法」という3つの株価算定方法を併用することを主張しました。
このように複数の株価算定方法を用いる場合、それぞれの算定結果をどのような割合で用いるかが問題となります。算定方法ごとの重要度を加味して平均額を算出する必要があるからです。このことを「加重平均」と呼びます。
この点、本件における加重平均の割合について、申立人は「等しい割合」を主張しました。なぜなら、各算定方法には一長一短があるため、用い方に差を設けることはできないと考えたのです。
つまり「収益還元法」「取引事例法」「類似会社比較法」それぞれの算定方法で算出した価格について、等しい割合で平均した金額を株式売買価格とすべきというのが、申立人側による主張の内容です。
以上から、本件で問題となった2400株の売買価格について、申立人が主張した具体的な金額は次のようになりました。
①取引事例法 ⇒ 1億3333万3000円
②収益還元法 ⇒ 1億63万1000円
③類似会社比較法 ⇒ 5382万8000円
加重平均額(=(①+②+③)÷3) ⇒ 9593万円
相手方が主張した売買価格
一方で相手方は、「純資産法」「収益還元法」「配当還元法」という3つの株価算定方法を併用することを主張しました。
なお、加重平均の割合は「純資産法」が70%、「収益還元法」が20%、「配当還元法」が10%です。このことから、相手方が最も重視している算定方法は「純資産法」であることがわかります。
以上から、本件の2400株の売買価格について、相手方は次のような金額を主張しました。
①純資産法 ⇒ 1770万8800円
②収益還元法 ⇒ 1688万777円
③配当還元法 ⇒ 0円
加重平均額(=(①×70+②×20+③×10)÷100) ⇒ 1577万2315万円
株価算定方法に関する判例において各当事者が主張した株価算定方法について
次に、申立人・相手方の主張に登場した株価算定方法について、一つずつ詳しく検討していきましょう。まずは、「収益還元法」についてです。
「収益還元法」について
「収益還元法」は、大きく分類すると「インカムアプローチ」と呼ばれる株価算定方法に属します。
ここにいう「インカム」とは、会社が将来にわたってもたらすことが予想される収益のことです。将来予想される事業の拡大(または縮小)を株価に織り込むことができるので、今後も事業を継続する予定の「継続会社」の株価を適切に算定できる手法だと言われています。
また収益還元法では、将来の価値(予想される収益)をもとにして、現在の価値(株価)を算定します。このように「将来の価値を現在の価値に引き直す」必要があるため、一定の割引率による割引きを行うのが一般的です。
なおインカムアプローチに属する株価算定方法には、ここで扱う「収益還元法」の他に、後述する「配当還元法」も存在します。収益還元法と配当還元法の相違点は、算定の基礎となる「インカム」のとらえ方に起因します。
収益還元法における「インカム」は、会社の業績を全体的に考慮したうえで予測される「収益」です。これに対して、配当還元法における「インカム」は、株主が将来受け取ることが予測される「配当」です。
「収益還元法」に関する申立人の主張
テレネット社は将来も事業を継続していく「継続会社」なので、将来の業績予想を株価に織り込む「収益還元法」と非常に相性が良いと言えます。そのこともあり、収益還元法を採用すること自体について、申立人・相手方間に争いはありません。
むしろ重要なのは、「収益還元法による計算の基礎とすべきA社の業績の範囲」です。この点について申立人は、販管費が落ち着き業績が安定した平成18年3月期以降の数値のみに限定して、将来の収益を見積もる基礎とすべき旨を主張しています。
なお、申立人がテレネット社に対して譲渡承認請求をしたのは平成19年3月です。したがって、Bが算定の基礎として主張しているのは、直近2期の業績のみということになります。
「収益還元法」に関する相手方の主張
これに対して相手方は、将来の業績予測を基礎とする「収益還元法」が持つ不確実性を強調しています。不確実な将来の業績を予測するには、算定の基礎とすべき実績は最低でも3~5年分必要だと主張しているのです。
具体的には、過去3年の業績の実績値を平均した税引後利益(経常利益から、経常利益に実効税率42%を乗じて算出した税金費用を控除した金額)をもとに、10.44%の割引率による割引きを行い、1688万777円という金額を算出しました。
この点で、直近2期の業績のみ参照すれば足りるとした申立人の主張とは大きく異なります。また、相手方が収益還元法による算定結果を20%しか反映すべきでないと主張したのも、やはり収益還元法の持つ不確実性を考慮したためです。
裁判所の判断
以上の主張を踏まえて、裁判所は株価算定に「収益還元法」を用いるべきとの判断を下しました。また、その際に算定の基礎とすべきテレネット社の業績について、平成18年3月期と平成19年3月期の直近2期のみに限定すべきとも判断しました。
直近2期の業績のみに限定して算定すべきとしたのは、テレネット社を「設立から間もない成長企業」として認定したのが理由です。
つまり、設立から業績安定までの期間は、テレネット社の事業が軌道に乗るための準備期間に過ぎないと判断したのです。準備期間の業績を株価算定の基礎に含めると、テレネット社の株価の過小評価になってしまうというわけです。
また裁判所は、直近2期の業績のみで「収益還元法」による算定が可能だと判断したのですから、相手方が強調したほどの不確実性を持つ算定方法だとは考えていないことがわかります。
具体的な金額としては、次のように算出しました。
まず平成18年3月期及び平成19年3月期の経常利益から、その平均値に実効税率(42%)を乗じて算出した税金額を控除して、予想税引後利益を算出します。そこから10%の割引率による割引きを行います。
その結果、1株当たり1万2929円という売買価格を算出しました。
「配当還元法」について
次は、相手方だけが採用を主張した「配当還元法」について見ていきましょう。
インカムアプローチに分類される株価算定方法
前述の通り、配当還元法は「インカムアプローチ」に分類されます。また、算定の基礎となる「インカム」については、株主が将来受け取る「配当」ととらえる考え方でもあります。
「配当還元法」に関する申立人の主張
申立人は、還元配当法の採用を否定する理由として、「本件株式がテレネット社の全株式の40%にあたる」という点を挙げています。冒頭で述べたように、テレネット社の発行済株式総数は6,000株ですから、本件で問題となっている2400株は全株式の40%に相当するのです。
この点、申立人は「配当還元法」について、もっぱら配当を受けることを主な目的として株式を取得する「少量株主(発行済株式の総数の1%から3%未満の株式を有する株主)」について用いるべき評価方法であると主張しています。
したがって、本件のように大量の株式を売買するような場合には、配当が株式取得の主目的となるとは考えにくく、「配当還元法」を用いて売買価格を算定することは不適切だというわけです。
他には、「テレネット社にこれまで配当実績が存在しない」という点についても、還元配当法を用いるべきでない理由として挙げられています。
「配当還元法」に関する相手方の主張
一方で相手方は、還元配当法の採用を肯定する理由として、「テレネット社の経営を支配しているのは申立人ではない」という点を挙げています。
つまり、申立人の保有株式数は2,400株である一方、相手方の保有株式数は3,600株です。筆頭株主はあくまでも相手方であって、申立人ではありません。
問題となっている2400株が筆頭株主のものでない以上、その取得目的には配当を受けることが多少なりとも含まれているはずだ、というわけです。
もっとも、テレネット社に配当実績がないのは事実なので、「配当還元法による算定結果は10%しか反映しない」とも主張しているのです。具体的な売買価格についても、同様の理由で0円という金額を主張しています。
裁判所の判断
裁判所は、配当還元法を用いるべきでないと判断しました。その理由について、裁判所は「経営権の移動」という言葉を使っています。
すなわち、相手方が指定買取人として申立人の保有する2,400株を買い取ることで、相手方はテレネット社の全株式にあたる6,000株を保有することになります。その結果、相手方はテレネット社の経営を完全に支配することができます。つまり、本件の2,400株の買取りによって、テレネット社の経営権が相手方へ移動する結果となるわけです。
このように経営権が移動する場面において、株式取得者が配当を目的としているとは考え難く、「配当還元法を用いる基礎に欠ける」との判断につながりました。
「純資産法」について
次は、相手方のみが採用を主張した「純資産法」について見ていきましょう。
コストアプローチに分類される株価算定方法
純資産法は、「コストアプローチ」に分類される算定手法です。
コストアプローチは、「会社が現に保有する資産の価値を、そのまま株価にも反映させる」という考え方に基づいています。
資産の評価額という明確な数値を基礎とするので、客観的な算定方法だと言われます。その一方で、インカムアプローチのように将来的な収益力の変動を考慮することができないことから、継続会社の株価を算定するには不向きだとも言われます。
具体的な算定方法としては、会計帳簿上の純資産額を基礎として計算を行います。
「純資産法」に関する申立人の主張
申立人は、純資産法による算定を否定しています。
その理由としては、①テレネット社は清算を予定していない(継続会社である)こと、②成長企業であるテレネット社は今後業績の好転が見込める(将来的な収益力の変動が大きい)こと、③テレネット社は不動産等の固定資産を保有していない、といった点を挙げています。
「純資産法」に関する相手方の主張
一方で相手方は、純資産法を「株式評価の大原則」であるとして、純資産法による算定を強く主張しています。純資産法による計算結果を70%も売買価格に反映させるべきと主張している点からも、いかに純資産法を重視しているかが分かります。
なお、「将来の収益力を評価できない」という純資産法のデメリットについては、「業績の変動が激しいテレネット社において、不確実性の大きな収益還元法はうまく機能せず、結果的に純資産法がもっともすぐれている」とのロジックでカバーしています。
裁判所の判断
裁判所は、申立人の主張とおおむね同様の理由で、純資産法による株価算定を否定しました。
「取引事例法」「類似会社比較法」について
最後に、申立人のみが採用を主張した「取引事例法」「類似会社比較法」について見ていきましょう。
マーケットアプローチに分類される株価算定方法
「取引事例法」と「類似会社比較法」は、いずれも「マーケットアプローチ」に分類される株価算定方法です。
マーケットアプローチでは、問題となっている株式について、参考となる比較対象を選定します。比較対象となるのが過去の取引事例であれば「取引事例法」、比較対象が類似会社の株価であれば「類似会社比較法」となります。いずれも、比較対象における株価(マーケット)を参考にすることから、マーケットアプローチと呼ばれます。
具体的には、「取引事例法」であれば、問題となっている株式について、過去の取引事例における株価を参考とします。「過去に同じような条件で売買されたときの株価が〇〇円だったということは、今回もそれくらいの株価になるはずだ」というわけです。
一方「類似会社比較法」では、問題となっている会社と業態・規模・成長性などが類似した上場会社の株価を比較対象とします。「同じような条件の他社の株価が〇〇円ということは、この会社の株価もそれくらいになるはずだ」というわけです。
「取引事例法」「類似会社比較法」に関する申立人の主張
申立人は、取引事例法を用いて算定すべきとの主張に関して、自身が2年前に行った2件の取引を「過去の取引事例」として挙げています。
一方、類似会社比較法を用いて算定すべきとの主張に関しては、参考にすべき「類似会社」を9社リストアップしています。
「取引事例法」「類似会社比較法」に関する相手方の主張
これに対して相手方は、申立人が挙げた「過去の取引事例」につき、2年も前なので参考にならないとしています。また、申立人が挙げた「類似会社」についても、業態が異なるので参考にならないとしています。
裁判所の判断
裁判所は、取引事例法と類似会社比較法のいずれも、本事案での利用を否定しました。
取引事例法を否定するに際しては、申立人の挙げた取引事例が2年前のものである点などに触れ、株価算定の参考にはならないとしました。
類似会社比較法を否定するに際しては、申立人が挙げた「類似会社」はテレネット社と規模が違うという点に触れ、こちらも株価算定の参考にならないとしました。
裁判所(株価算定方法に関する判例)の結論について
以上をまとめると、裁判所が本事案において株価算定方法として採用できるとしたのは、「収益還元法」のみということになります。すなわち、裁判所は本事案において、「収益還元法のみを用いてテレネット社の株価を算定すべき」との立場に立ったのです。
その背景としてもっとも大きいのは、テレネット社が「成長企業」として認定されたことにあるでしょう。今後の成長が見込まれる会社の株価を正しく算定するには、将来の収益変動を株価に織り込む「収益還元法」が適しているというのが、裁判所の考え方だと言えるのです。
その結果、収益還元法によって算出された「1株当たり1万2929円」という価格が、本件で問題となった2400株の売買価格として決定されることとなりました。