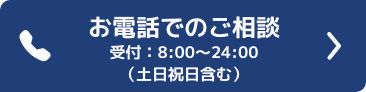株価算定方法に関する判例(Mika社事件)!
今回扱う裁判例で問題となったのは、非上場株式売買価格です。
そもそも非上場株式には、市場価格が存在しません。そのため、非上場株式の価値を算定するには、しばしば困難が伴います。株価を決めようにも、分かりやすい客観的な基準がないからです。
特に、譲渡制限株式の譲渡を会社が承認しなかった場合は、非常に厄介です。
会社が株式の譲渡を承認しない場合、当該株式は会社(または指定買取人)が買い取らなければなりません。その際に、買取価格をいくらにするかという点について、当事者間で協議が決裂してしまうことが大変多いのです。
この場合、裁判所に対して、株式価格決定申立がなされます。平たく言うと、会社や株主(または株式取得者)といった当事者だけでは株式買取価格を決めることができないので、代わりに裁判所に決めてもらおうというわけです。
今回の裁判例も、そうした、株式価格決定申立がなされた事案なのです。
株価算定方法に関する判例:Mika社事件の概要
今回の裁判例で問題となった譲渡制限株式を発行したのは、スポーツ用品および工業用ゴム製品の製造・販売を行うMika社です。(※裁判例には実際の会社名が記載されていますが、本稿では仮の名称で記載します。他の会社についても同様です)
会社(Mika社)のデータ
非上場会社であるMika社は、すべての株式に譲渡制限がなされています。
また、Mika社の発行済株式総数は240万株です。総資産として119億9174万1553円を計上しており、そのうち株主資本(株主が出資した資金に利益剰余金を加えた金額)は70億6336万6247円となっています。
売上高については、裁判時点の直近3期で、59億3688万2956円(平成16年11月期)、58億609万4512円(平成17年11月期)、60億3376万8033円(平成18年11月期)となっています。ほぼ60億円前後で推移している状況です。
裁判に至った経緯
「Mikaホールディング社」と「S社」が、Mika社の株主から同社株を譲り受けます。(※なお、Mikaホールディング社とS社は、当該株式の譲渡以前から、合計38万1220株のMika社株を保有していました。議決権ベースで考えると、26.17%のMika社株を保有していたことになります。つまり、両社はもともとMika社の大株主だったということになります)
しかし当該株式の譲渡について、Mika社は承認をしませんでした。
当該株式は譲渡制限株式なので、譲渡の承認がない場合には、会社(または指定買取人)が買い取らなければなりません。本件では、Mika社および同社の代表取締役Aが買い取ることになりました。(※代表取締役Aは、指定買取人としてMika社に指定されました)
しかし、当該株式買取価格について、当事者間での協議がまとまりません。そこで、Mika社サイドとMikaホールディング社サイドの双方が、当該株式について、株式価格決定申立を行いました。
なお、裁判例ではMika社サイドを「買い手」、Mikaホールディング社サイドを「売り手」と表記しています。本稿もこの表記にならって、次項から「買い手サイド」「売り手サイド」との表記を用いて進めていきます。
株価算定方法に関する判例で当事者が主張した「株価算定基準」について
次に、今回の裁判例において、どのような株価算定基準が問題となったのでしょうか。
裁判例に登場した3つの株価算定基準
まず、裁判例ではどのような株価算定基準が争われたのか、簡単に確認してみましょう。
買い手サイドが主張した株価算定基準
買い手サイドは、「DCF方式」と「ゴードン・モデル方式」を併用して算定することを主張しました。それぞれの方式で算出した株価を「足して2で割った価格」(裁判例では「50:50の加重平均額」と表現されています)を、当該株式の株価とすべき旨主張したのです。
具体的な株価の算出についての主張は、次の通りです。(※金額はすべて1株当たりの価格です)
①DCF方式による評価額(2038円~2640円)の平均額(2339円)と、②ゴードン・モデル方式による評価額(376円~447円)の平均額(411円)について、③50:50の加重平均額(1375円)を求めます。
その結果、買い手サイドは「1株当たり1375円」という株価を主張しました。
売り手サイドが主張した株価算定基準
これに対して売り手サイドは、「DCF方式」と「純資産方式」による算定を主張しました。それぞれの「足して2で割った価格」(50:50の加重平均額)を株価とすべき旨は、A社の主張と同様でした。
具体的な株価は、次のように算出しました。(※金額はすべて1株当たりの価格です)
①DCF方式による評価額(5481円~6097円)と、②純資産方式による評価額(4052円)について、③両者を50:50とする加重平均額(4767円~5075円)を求めます。
さらに、③の中間値(4921円)を求めたうえで、「1株当たり4921円」という株価を主張しました。
株価算定方法に関する判例の株価算定基準の全体像
以上のように、今回の裁判例では「DCF方式」「ゴードン・モデル方式」「純資産方式」といった3つの株価算定基準が登場しています。
これらの基準は、それぞれ一体どのような位置づけとなるのでしょうか。その検討に入る前に、「株価算定基準の全体像」について概観しておきましょう。
一般的に、株価の算定基準は、大きく次の3つに分類されます。
- コストアプローチ
- マーケットアプローチ
- インカムアプローチ
では、それぞれの分類について見ていきましょう。
コストアプローチ
1番目の「コストアプローチ」は、「その会社が保有する資産の価値」に着目して株価を算定する方法です。「資産から負債を差し引いた額が大きいほど、企業価値すなわち株価も高くなるはず」という考え方だと言えるでしょう。
マーケットアプローチ
2番目の「マーケットアプローチ」は、「その会社が属する業界一般の株価」に着目する考え方です。同業他社や類似企業の株式市場(マーケット)における価値を評価基準とすることから、マーケットアプローチと呼ばれています。
なお、マーケットアプローチに該当する株価算定基準は、今回の裁判例には登場していません。
インカムアプローチ
3番目の「インカムアプローチ」では、「その会社が将来にわたって生み出す経済的利益(インカム)」に着目します。インカムアプローチをさらに細かく分類すると、会社が生み出す利益を総合的に判断する「収益還元方式」や、株主が受ける利益を重視して判断する「配当還元方式」に分けることができます。
「収益還元方式」について、裁判例は「評価対象会社から将来期待することができる経済的利益を当該利益の変動リスク等を反映した割引率により現在価値に割り引き、株主等価値を算定する方式」と説明しています。
一方「配当還元方式」について、裁判例では「将来給付が予測される利益配当額を現在の価値に引き直して株式価値を算定する方法」と説明されています。
今回の裁判例(株価算定方法に関する判例)で問題となった株価算定基準の位置づけ
上記の全体像の中で、今回の裁判例に登場した3つの株価算定基準は、どの種類に分類されるものなのでしょうか。
「DCF方式」 収益還元法(インカムアプローチ)
「DCF方式」は、インカムアプローチの「収益還元方式」に分類されます。
その具体的な内容について、裁判例では次のように説明されています。
「将来のフリー・キャッシュ・フロー(=企業の事業活動によって得られた収入から事業活動維持のために必要な投資を差し引いた金額)を見積り、年次ごとに割引率を用いて求めた現在価値の総和を求め、当該現在価値に事業外資産を加算したうえで企業価値を算出し、負債の時価を減算して株式等価値を算出して株主が将来得られると期待できる利益(リターン)を算定する方法」
この説明の中で、特に注目すべきは「現在価値」という言葉です。つまり、現在の事業活動をトータルに考慮して算出した「現在の企業価値」を基礎として、株価を算定するのが「DCF方式」なのです。会社が保有する資産だけでなく、現在行っているビジネス自体が今後生み出すであろう価値も考慮できるという点に、「DCF方式」の大きな特長があります。
「DCF方式」による実際の計算は、多くの要素を勘案しながら行います。具体的には、まず将来のフリー・キャッシュ・フローを見積もった後、永久成長率・市場リスクプレミアム・負債コストなどを考慮して割引を行います。さらに非流動性ディスカウント(市場価格が存在しないことを理由とする値引き)を行い、最終的な株価を算定します。
「ゴードン・モデル方式」 配当還元方式(インカムアプローチ)
一方、「ゴードン・モデル方式」は、インカムアプローチの「配当還元方式」に分類されます。
「ゴードン・モデル方式」に関する裁判例の説明は、次の通りです。
「企業が獲得した利益のうち配当に回されなかった内部留保額は再投資によって将来利益を生み、配当の増加を期待できるものとして評価する方法」
この説明の中で、特に注目すべきは「内部留保額」という言葉です。というのも、株主に対して将来給付されることが予測される配当額を基礎として株式価値を算定する「配当還元方式」の中でも、「企業の内部留保額を株価算定の基礎に加える」点に「ゴードン・モデル方式」の大きな特徴があるからです。
「純資産方式」 コストアプローチ
「純資産方式」は、コストアプローチに該当します。
なお、裁判例は「純資産方式」について、「企業の有する資産から負債の額を控除した株主の持分としての純資産に着目して価値を評価する方法」と説明しています。
つまり、「会社が保有している資産の評価額」を株価算定の基礎とする方法ということです。会社のビジネスが今後生み出すであろう利益は評価の対象とならないので、会社を清算するような局面に適した算定方法だと言えるでしょう。
各株価算定基準に対する裁判所(株価算定方法に関する判例)の評価について
以上の全体像をもとに、今回の裁判例で登場した算定基準が、裁判所によってどのように評価されたのか見ていきましょう。
「DCF方式」に対する裁判所の評価
継続企業の株価を評価するのに適した手法
買い手サイド・売り手サイドともに主張した「DCF方式」は、裁判所によっても肯定的に評価されています。
そのポイントは、当該株式を発行したMika社が「継続企業」であるという点にあります。
ここでいう「継続企業」とは、「今後も継続して事業活動を行っていくことが想定される企業」といった意味で使われています。
つまり、Mika社は継続企業として今後も利益を生み出していく以上、「会社が将来にわたって生み出す収益」を重視する「収益還元方式」は、適切な株価算定基準だと判断されたのです。
そのうえで、裁判所は「DCF方式」について、「収益還元方式」の中でも特に理論的な方法と評価しています。したがって「DCF方式」は、Mika社の株価を算定するのに適切な算定基準だと判断されたのです。
株式を発行する会社側の立場に即した株価算定基準
また、裁判所は「DCF方式」について、「会社の立場から相当な評価方式」とも評しています。
そのポイントは、「株式を発行した会社自身は、株式からの配当を期待するものではない」という点にあります。
つまり、会社が自社の株式を売買する目的は、配当を得ることにはありません。そもそも会社が自社の株式から配当を受けることは不可能です。そうである以上、会社の立場から相当な株価算定基準は、配当に重きを置く「配当還元方式」ではなく、会社のビジネス全体を考慮する「収益還元方式」(その中でも特に理論的な「DCF方式」)だということになるのです。
「ゴードン・モデル方式」に対する裁判所の評価
「配当還元方式」の中でも特に優れた方法
一方、買い手サイドだけが主張した「ゴードン・モデル方式」についても、裁判所は肯定的に評価しました。「配当還元方式」の株価算定法の中でも、特に優れた方法という評価をしています。
そのポイントは、「ゴードン・モデル方式」が「内部留保も株価算定の基礎とする方法」だという点にあります。
というのも、「配当還元方式」の株価算定法には「実際配当還元法」や「標準配当還元法」といったものがありますが、いずれも「配当に回されなかった内部留保額」は考慮に入れません。これに対して、「ゴードン・モデル方式」では「内部留保額は再投資によって配当の増加につながる」という考え方をします。
そのため、「ゴードン・モデル方式」は他の手法よりもきめ細かい計算が可能であり、「配当還元方式」の中でも特に優れた方法として評価されているのです。
株主の立場から相当な株価算定基準
また、裁判所は「ゴードン・モデル方式」について、「株主の立場から相当な評価方式」とも評しています。
そのポイントは、「株式の売買は株主の投資回収の方法である」という点にあります。つまり、配当を受けることを期待して株を購入する株主にとって、配当額を基礎として株価を算定する「配当還元方式」が相当な方法だと考えられるのです。
そして、「配当還元方式」の中でも特に優れた「ゴードン・モデル方式」こそ、株主の立場に即した株価算定基準だと評価されたのです。
もっとも、本事案で「ゴードン・モデル方式」を主張したのは、株主である売り手サイドではなく、当該株式を発行した買い手サイドでした。
つまり裁判所は、買い手サイドが主張した算定基準について、売り手サイドに適切なものと判断したということになります。その意味では、当事者の意図とは異なる判断が裁判所によってなされたと言えるでしょう。
「純資産方式」に対する裁判所の評価
継続企業の株価を評価するのには不適切
売り手サイドだけが主張した「純資産方式」について、裁判所は否定的に評価しています。
そのポイントは、「純資産方式」による評価が「一時点の純資産に基づいた価値評価」であるという点にあります。つまり、「純資産方式」では将来の収益を反映できないため、今後も事業を継続する会社の株価を算定するには不向きだと考えられるのです。
そのため、継続企業であるMika社の株価を算定するには、「純資産方式」は不適切だと判断されました。
裁判所(株価算定方法に関する判例)による株価の算出
以上を踏まえて、裁判所による株価の算出プロセスについて、確認していきましょう。
裁判所が採用した算定方式について
裁判所は結論として、「DCF方式とゴードン・モデル方式を1:1で折衷する方式」を採用しました。
ポイントは、「当事者の双方を対等の立場におく」という考え方です。すなわち、本件は会社法の規定による株式買取請求の事案であるため、一般的な株式売買の場面とは異なり、買い手・売り手の双方をまったく対等の立場に置くべきだと考えたのです。
こうした考え方から、買い手(会社)の立場から相当な「DCF方式」と、売り手(株主)の立場から相当な「ゴードン・モデル方式」を、それぞれ対等に1:1で折衷するという結論が採用されました。
本件では、たまたま「DCF方式」と「ゴードン・モデル方式」のどちらも買い手サイドが主張したため、裁判所の結論は買い手サイドの主張をそのまま採用したようにも見えます。しかし、実際には「買い手・売り手の双方を対等に扱う」という考え方に基づく結論となっている点に、注意が必要です。
「DCF方式」による株価の算出
「DCF方式」を用いるべきという点は、買い手サイドと売り手サイド双方の主張に共通していました。
しかし、実際に算出された株価は、それぞれ異なります。買い手サイドは「1株当たり1375円」、売り手サイドは「1株当たり4921円」の株価を主張しました。
この点、裁判所は買い手サイドの主張した「1株当たり1375円」を採用しました。その判断の内容について、確認していきましょう。
永久成長率
「DCF方式」では、算定のベースとなる「将来のフリー・キャッシュ・フロー」を現在の価値へ割り引くために、様々な要素を考慮します。そのひとつが、会社の永久成長率です。
この点、買い手サイド・売り手サイドともに、理由付けは若干異なりますが、永久成長率を0%として計算しました。そして、裁判所もその判断を合理的なものだと判断しました。
つまり、Mika社は将来も同程度の事業規模にあるものとみなして、株価が算定されたことになります。
市場リスクプレミアム
割引率を考慮するうえで重要となるのが、市場リスクプレミアムです。将来にわたって予想される市場の変動を、株価に織り込むための指標です。
この点、買い手サイドは「1955年1月以降」のデータを基礎とする数値(8.0%)を主張しました。これに対して、売り手サイドは「高度成長期を除いた1978年1月以降」のデータを基礎とする数値(4.0%)を主張しました。
そして裁判所は、より長期間のデータを基礎としている買い手サイドの主張を、合理的なものとして認定したのです。
負債コスト
割引率を考慮する際には、負債コストも重要となります。
負債コストとは、平たく言えば「負債によって生ずる支払利息の負担」のことです。会社の負債額に応じて将来にわたって見込まれる負担額を、株価にも織り込もうという考え方です。
この点、裁判所は買い手サイドの主張した「1.78%」という数値を、合理的なものとして認定しました。
非流動性ディスカウント
Mika社株は非上場株式なので、市場価格が存在しないことを理由とする値引き(非流動性ディスカウント)をすべきか否かが問題となります。
この点、買い手サイドは、Mika社株は非上場株式であるだけでなく、譲渡制限株式でもあるという点を重視しました。すなわち、Mika社株は流動性を著しく欠いており、当然に非流動性ディスカウントを考慮すべきというわけです。
これに対して、売り手サイドは、非流動性ディスカウントを考慮すべきでないと主張しました。その理由として、Mika社には自社株を売却する意思も予定もなく、売却コストを考慮する必要がないこと等が挙げられています。
裁判所は、買い手サイドの主張を合理的なものとして認定しました。つまり、非流動性ディスカウントによる値引きを肯定したのです。
裁判所の評価額
以上から、「DCF方式」に基づく本件株式の株価について、裁判所は買い手サイドが主張した算定プロセスを肯定したことになります。そのため、裁判所の評価額は「1株当たり2038円~2640円(平均額2339円)」というものになりました。
「ゴードン・モデル方式」による株価の算出
「ゴードン・モデル方式」による算出は、買い手サイドだけが主張したものです。そして、買い手サイドが主張した算出プロセスも含めて、裁判所はこれを合理的なものとして認定しています。
したがって、「ゴードン・モデル方式」に基づく本件株式の株価について、裁判所の評価額は「1株当たり376円~447円(平均額411円)」というものになりました。
株価算定方法に関する判例で最終的に決定された株価
以上を踏まえて、裁判所は「1株当たり2038円~2640円(平均額2339円)」と「1株当たり376円~447円(平均額411円)」を1:1で折衷し、「1株当たり1375円」という株価を決定しました。