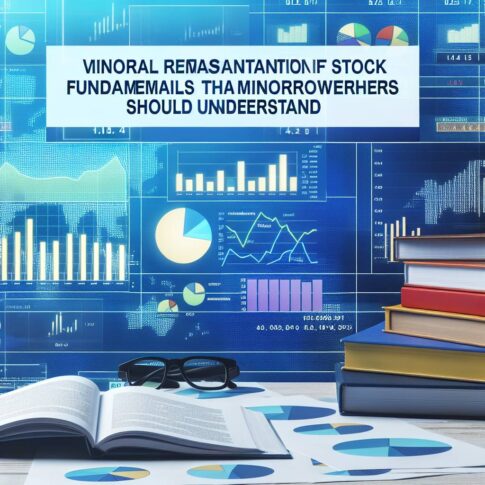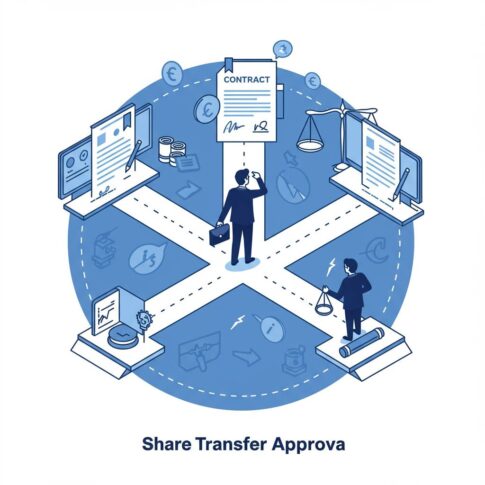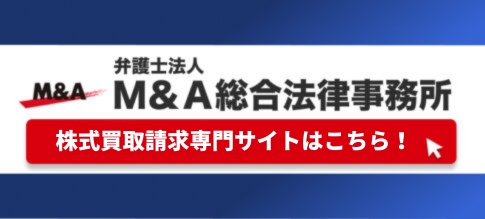「非上場株式の売却手続きで失敗してしまった」「思わぬトラブルに巻き込まれた」といった相談が、近年急増しています。実際、非上場株式の売却は上場株式と比べて複雑な法的手続きが必要となり、専門家でも見落としがちなポイントが数多く存在します。
当ブログでは、企業法務の実務経験20年以上の弁護士と、非上場株式取引のエキスパートである税理士の監修のもと、安全確実に非上場株式を売却するための法的チェックリストをご紹介します。
特に、中小企業のオーナーや同族会社の株主の方々に向けて、定款の確認から売買契約書の作成まで、具体的な事例を交えながら分かりやすく解説していきます。また、近年改正された会社法の規定や、国税庁の判断基準についても詳しく取り上げています。
この記事では、以下の5つの重要テーマについて、実務に即した形で詳しく解説していきます。非上場株式の売却をご検討中の方は、必ずご一読ください。法的リスクを最小限に抑え、スムーズな取引を実現するための重要な情報が満載です。
1. 【完全保存版】非上場株式の売却で失敗しないための法的手続き7ステップ
1. 【完全保存版】非上場株式の売却で失敗しないための法的手続き7ステップ
非上場株式の売却は、上場株式と比べて手続きが複雑で失敗するリスクが高いものです。特に法的な観点からのチェックを怠ると、取引が無効になったり、予期せぬトラブルに発展する可能性があります。
以下の7つのステップを順番に確認していくことで、安全な取引が実現できます。
Step1:定款の確認
まず会社の定款をチェックし、株式譲渡制限の有無を確認します。制限がある場合は、取締役会の承認が必要となります。
Step2:株主間契約の精査
既存の株主間で締結されている契約の有無を確認し、先買権や共同売却請求権などの制限事項をチェックします。
Step3:譲渡承認手続き
株式譲渡制限会社の場合、取締役会に譲渡承認請求を提出します。この際、譲渡価格や譲渡先の情報を明確に記載する必要があります。
Step4:株式評価
適正な譲渡価格を算定するため、純資産価額方式や類似業種比準方式などの評価方法を用いて、株式価値を算出します。
Step5:譲渡契約書の作成
弁護士のアドバイスを受けながら、表明保証条項や価格調整条項を含む譲渡契約書を作成します。
Step6:名義書換
株主名簿の書換手続きを行い、新しい株主として登録します。この手続きを怠ると、会社に対する株主としての権利行使ができません。
Step7:税務申告
株式譲渡所得に関する確定申告を行います。譲渡価格の妥当性について税務署から指摘されないよう、評価根拠を明確にしておくことが重要です。
これらの手続きは、専門家のサポートを受けながら進めることで、スムーズな売却が可能となります。特に第三者への売却の場合は、デューデリジェンスも含めた慎重な対応が求められます。
2. 税理士が解説!非上場株式の売却時に必ず確認すべき重要書類と法規制
2. 税理士が解説!非上場株式の売却時に必ず確認すべき重要書類と法規制
非上場株式の売却手続きを進める際、法的な観点から確認すべき重要書類があります。まず必須となるのが株主名簿です。これは株式の所有権を証明する基本的な書類で、名義が正確に記載されているか確認が必要です。
次に定款の確認が重要です。特に株式譲渡制限の有無をチェックしましょう。制限がある場合、取締役会の承認など追加の手続きが必要となります。また、株主間契約書が存在する場合は、優先買取権などの制限事項も確認が必要です。
売却時の価格算定根拠となる財務諸表も重要書類です。直近3期分の決算書、特に貸借対照表と損益計算書は必須となります。加えて、税務署への提出書類として譲渡所得に関する確定申告書の準備も忘れずに。
法規制面では、金融商品取引法の規制対象となるケースもあります。株主数が多い場合や、投資事業有限責任組合などのファンドが関与する場合は、追加の法的手続きが求められることがあります。
実務上のポイントとして、売却契約書の作成前に株式評価報告書を準備することをお勧めします。第三者機関による客観的な評価は、売却価格の妥当性を示す重要な根拠となります。
なお、相続や贈与により取得した株式の場合は、取得時の評価額を証明する書類も必要です。これは将来の譲渡所得の計算に影響するため、特に注意が必要な点です。
3. 知らないと損する!非上場株式の譲渡制限と定款確認の重要ポイント解説
3. 知らないと損する!非上場株式の譲渡制限と定款確認の重要ポイント解説
非上場株式の売却で最も重要なチェックポイントが「譲渡制限」です。会社法では、非上場会社の株式譲渡には原則として取締役会または株主総会の承認が必要と定められています。
まず確認すべきは定款の内容です。定款には譲渡制限に関する具体的な規定が記載されており、例えば「取締役会の承認を要する」「株主総会の特別決議を要する」などの条件が明記されています。これを見落として売却手続きを進めると、取引が無効となるリスクがあります。
次に注目すべきは、株主間契約の存在です。株主間で独自の譲渡制限を設けているケースも多く、この確認を怠ると思わぬトラブルに発展する可能性があります。
具体的な確認手順としては:
・定款の譲渡制限条項の確認
・株主間契約書の精査
・取締役会議事録の確認
・株主名簿の記載事項の確認
特に気をつけたいのが「先買権」の有無です。これは既存株主に優先的な購入権を与える規定で、多くの非上場企業で採用されています。この権利を無視した売却は、法的な紛争に発展するケースがあります。
また、譲渡承認手続きには通常1〜2ヶ月程度の期間を要します。売却を検討する際は、この期間も考慮に入れた計画が必要です。早め早めの準備が、スムーズな売却の鍵となります。
4. 実例から学ぶ!非上場株式売却で陥りやすい法的トラブルと対処法
4. 実例から学ぶ!非上場株式売却で陥りやすい法的トラブルと対処法
非上場株式の売却において、実際に発生した法的トラブルの事例から具体的な対処法を解説します。最も多いトラブルは、株主間契約における先買権条項の見落としです。売却を進めていたにもかかわらず、既存株主から先買権行使の申し出があり、予定していた売却先との取引が白紙になってしまうケースが報告されています。
次に注意すべきは、株式評価額の算定方法を巡る紛争です。一般的な純資産価額方式と、DCF法などの収益還元方式で大きな評価額の差が生じ、売り手と買い手の交渉が難航するケースが多発しています。このような場合、第三者機関による株価算定を活用することで、客観的な評価額の提示が可能となります。
また、相続により取得した非上場株式の売却では、相続税の取り扱いに関する認識の誤りが深刻なトラブルを引き起こしています。相続税の物納に使用した株式は売却できないため、事前に税理士への相談が不可欠です。
これらのトラブルを防ぐためには、株主間契約書の精査、適切な株価算定方法の選択、税務上の確認を事前に行うことが重要です。特に、M&A仲介会社や弁護士などの専門家に相談することで、潜在的なリスクを最小限に抑えることができます。
5. 経験者が警告!非上場株式の売買契約書作成時に必須の確認事項15選
5. 経験者が警告!非上場株式の売買契約書作成時に必須の確認事項15選
非上場株式の売買契約書作成時に見落としがちな重要事項をリスト化しました。M&A実務経験者の視点から、特に注意が必要な15の確認項目を解説します。
1. 株式譲渡制限の有無と承認手続き
2. 表明保証条項の範囲と期間
3. 株式の価格算定根拠
4. 決済方法と支払時期
5. 株主名簿の名義書換手続き
6. 株券の有無と受渡方法
7. 簿価の確認と税務上の影響
8. 瑕疵担保責任の範囲
9. 重要事実の開示義務
10. 反社会的勢力排除条項
11. 守秘義務条項の期間
12. 株主総会・取締役会の承認要否
13. 競業避止義務の有無
14. 紛争解決手段の明記
15. 契約解除条件の設定
特に重要なのは表明保証条項です。売主は財務諸表の正確性や簿外債務の不存在などを保証する必要があります。また、株式譲渡制限がある場合は、必ず事前に会社の承認を得ることが求められます。
これらの項目を事前にチェックすることで、売買後のトラブルを防ぎ、スムーズな取引が可能となります。法務部門や弁護士との連携も検討しましょう。