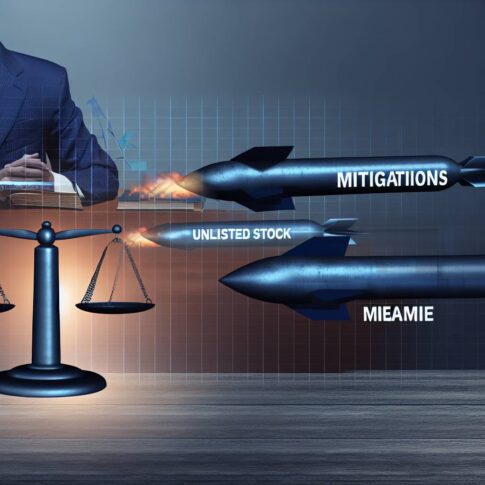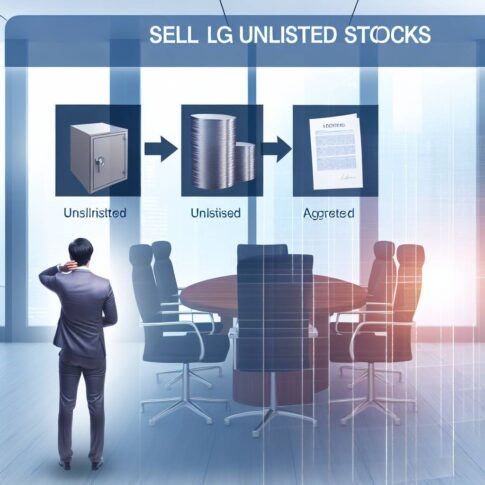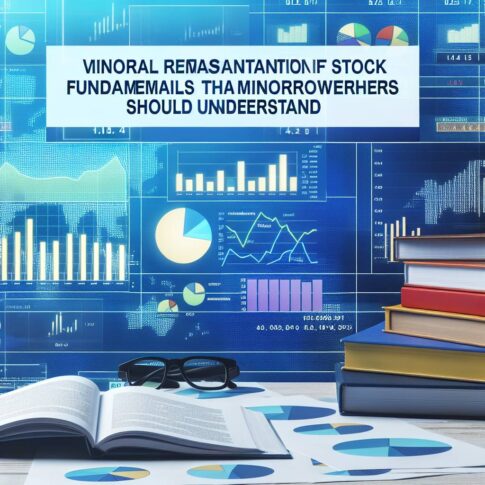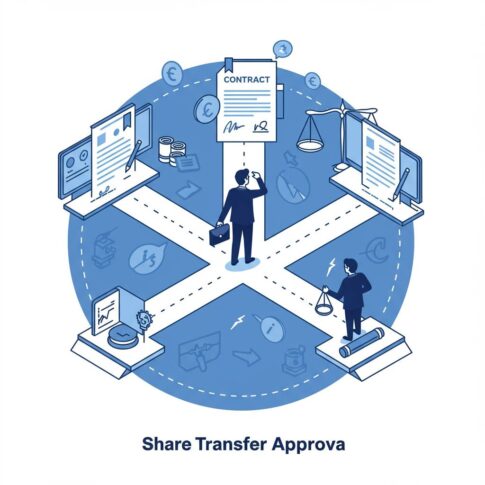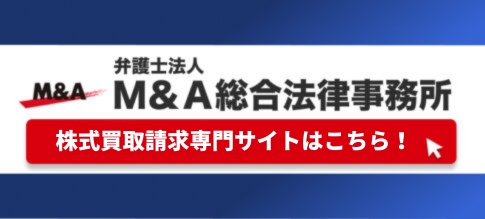非上場株式の株価算定は、企業の内部関係者や投資家にとって極めて重要なプロセスです。しかし、非上場企業という特性上、株価を正確に算定するのは非常に難しく、さまざまなトラブルが発生しがちです。この記事では、非上場株式の株価算定においてよくあるトラブルと、その対策について詳しく解説します。
まず、非上場株式の株価算定でよくあるトラブルの一つに、「適切な評価基準の選択」があります。非上場企業は、公開企業とは異なり、市場で取引されている株価が存在しないため、評価基準を選ぶことが難しくなります。DCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法)や市場アプローチ、コストアプローチなど、いくつかの方法がありますが、企業の状況に応じてどの方法を選ぶべきか慎重に判断する必要があります。
次に、「情報の不透明性」も大きなトラブル要因です。非上場企業は情報の開示が義務付けられていないため、外部からの情報収集が難しいことがあります。このような場合、内部情報の透明性を高めるために、企業内部での情報共有を進め、第三者機関の評価を受けることが有効です。これにより、情報不透明性による誤った算定を防止できます。
また、「利益相反」の問題も見過ごせません。株価算定にはさまざまな利害関係者が関与するため、特定の関係者に有利な結果を導くために不適切な操作が行われる可能性があります。これを防ぐためには、独立した第三者による公平な算定を行うことが重要です。信頼性の高い評価機関を選択し、専門家の意見を参考にすることで、利益相反を回避することができます。
これらのトラブルを未然に防ぐために、企業内でのコンプライアンス体制の強化や、定期的な内部監査の実施も重要なポイントです。また、株価算定プロセスにおけるガイドラインを策定し、関係者全員がその基準を理解し遵守することも有効な対策となります。
非上場株式の株価算定は、企業価値を正確に反映し、関係者全員が納得できる形で行われるべきです。適切な対策を講じることで、トラブルを未然に防ぎ、公正で透明性のある株価算定を実現しましょう。