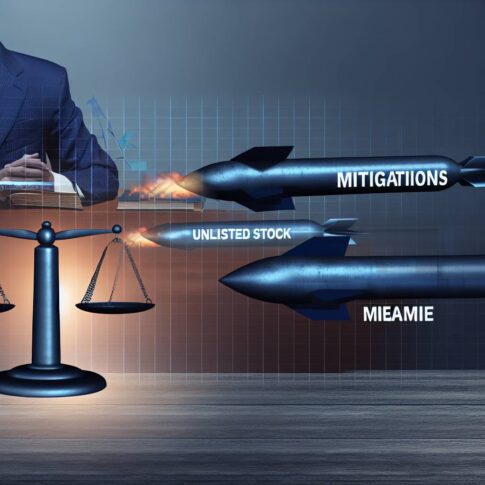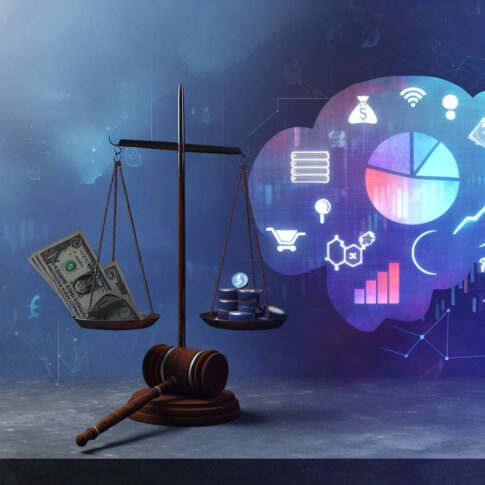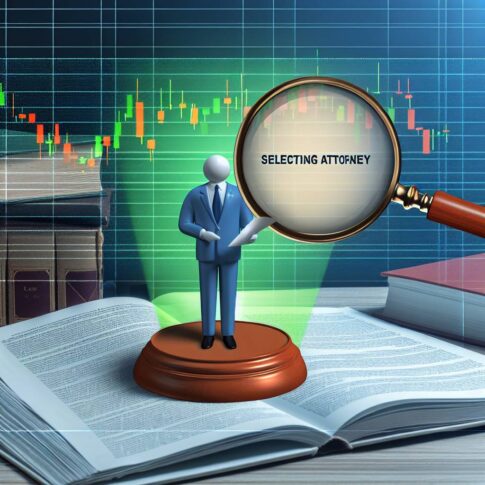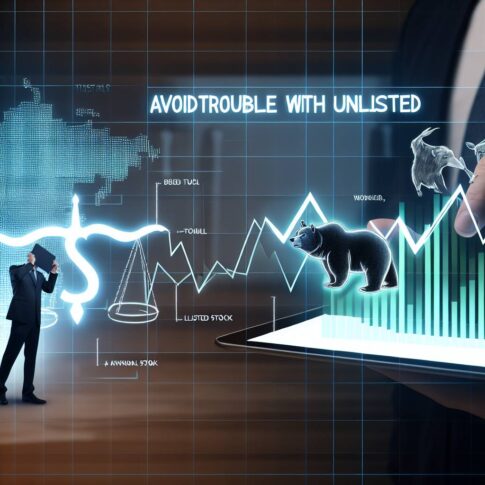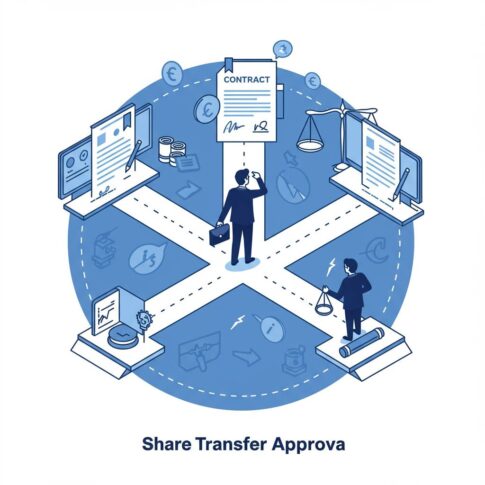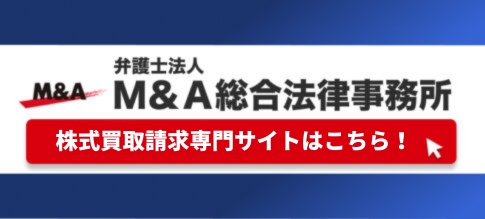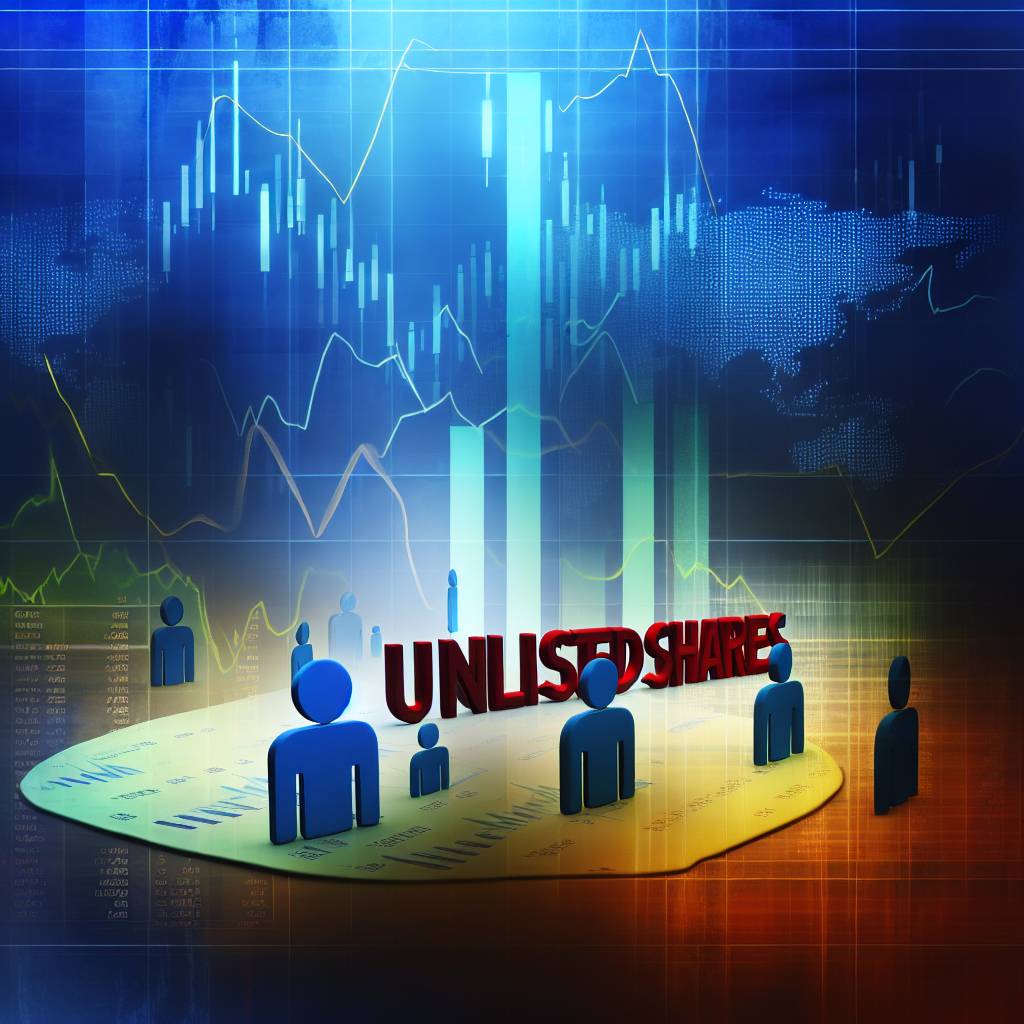 非上場株式は、上場株式と異なり市場での取引が行われないため、その価値を客観的に評価するのが難しいとされています。このため、株価算定には専門的な知識と慎重なアプローチが必要です。この記事では、非上場株式のリスク管理に焦点を当て、株価算定の基本とトラブル事例を通じて注意すべきポイントを詳しく解説します。
非上場株式は、上場株式と異なり市場での取引が行われないため、その価値を客観的に評価するのが難しいとされています。このため、株価算定には専門的な知識と慎重なアプローチが必要です。この記事では、非上場株式のリスク管理に焦点を当て、株価算定の基本とトラブル事例を通じて注意すべきポイントを詳しく解説します。
まず、株価算定の基本について説明します。非上場株式の株価を算定する際には、一般的にDCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法)や市場アプローチ、コストアプローチなどが用いられます。DCF法は将来のキャッシュフローを現在価値に割り引いて株価を算定する方法で、市場アプローチは類似企業の市場データを基に評価を行う方法です。コストアプローチは、企業の純資産価値を基に算定する手法です。これらの方法を組み合わせ、複数の視点からバランスの取れた評価を行うことが求められます。
次に、非上場株式のリスク管理におけるトラブル事例を見ていきましょう。非上場株式は流動性が低いため、売却が難しく、価値が下落するリスクがあります。ある企業では、株価算定を甘く見積もった結果、株式の価値が実際よりも高く評価され、その後の資金調達に失敗したケースが報告されています。このようなトラブルを回避するためには、専門家のアドバイスを受け、綿密な市場調査を行うことが重要です。
また、株主間で意見が対立したり、株式譲渡に関するトラブルが発生することもあります。特に、家族経営の企業では、株価算定に関する意見の相違が親族間の対立を引き起こすことがあるため、事前に明確な合意を形成しておくことが大切です。
非上場株式のリスク管理においては、株価算定の精度を高めることが極めて重要です。専門家による第三者評価を活用したり、透明性の高い情報開示を心がけることで、リスクを低減し、トラブルを未然に防ぐことが可能です。
このように、非上場株式には特有のリスクが存在するため、投資家や企業経営者は株価算定とリスク管理に細心の注意を払う必要があります。この記事を通じて、非上場株式のリスク管理に関する理解を深め、適切な対策を講じる一助となれば幸いです。