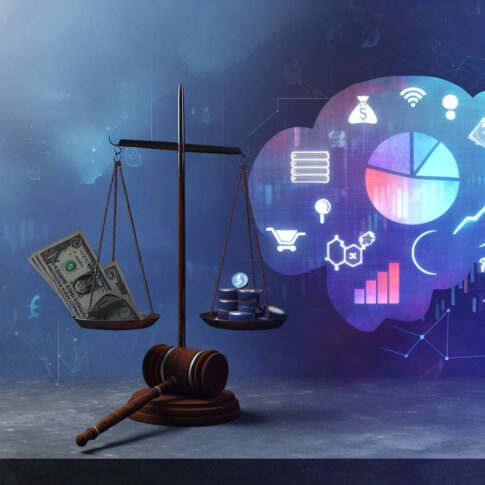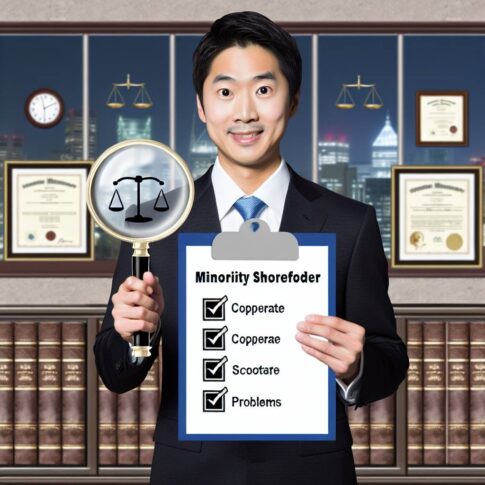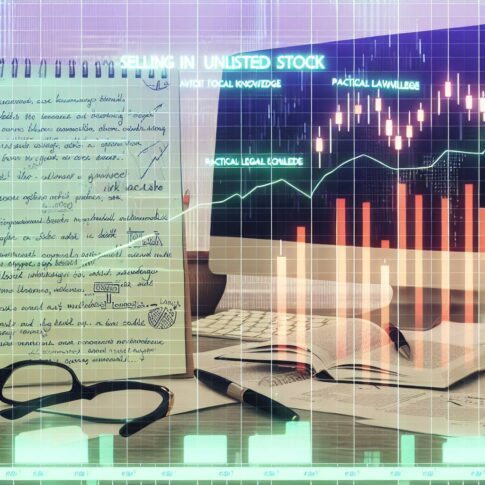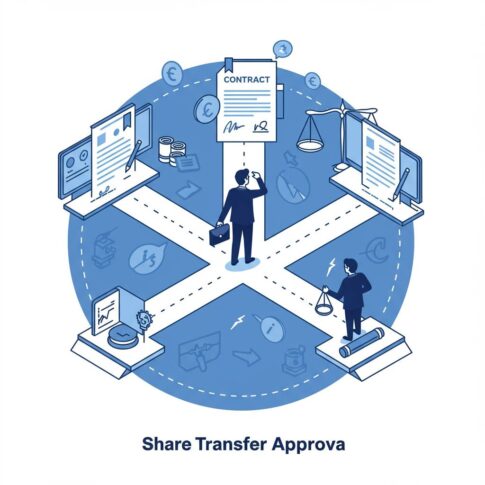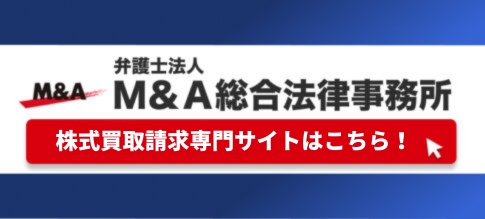非上場株式の株価算定は、企業の買収や合併、事業承継、株主間のトラブル解決など、さまざまな場面で必要となります。しかし、上場株式とは異なり、市場価格が存在しないため、その評価は容易ではありません。ここでは、弁護士の視点から非上場株式の株価算定における注意点について詳しく解説いたします。
まず第一に、非上場株式の評価方法には、主に三つのアプローチがあります。「市場アプローチ」、「収益アプローチ」、「コストアプローチ」です。市場アプローチは類似企業の株価を参考にしますが、適用には慎重さが求められます。同業他社といえども、業績や経営環境が異なるケースが多いため、単純な比較は避けるべきです。
次に、収益アプローチは将来の収益を割り引いて現在価値を算出する方法です。この方法は企業の収益力を反映しやすいのですが、将来の予測には不確実性が伴います。特に収益予測を行う際には、過去の業績だけでなく、業界動向や経済情勢を考慮することが重要です。
コストアプローチについては、企業の純資産価額を基にした評価を行います。これは、企業の解散価値を反映したものであり、特に資産が多い企業や、資産の流動性が高い企業に対して有効です。しかし、無形資産の価値が大きい企業の場合、この方法は適用が難しいことがあります。
これらのアプローチを単独で用いるのではなく、複数のアプローチを組み合わせることで、より精度の高い評価を行うことができます。また、適切な割引率の選定や、評価基準の透明性確保も重要です。これらのプロセスには、法的な知識や実務経験が求められるため、弁護士や公認会計士、税理士など専門家の協力を仰ぐことが賢明です。
さらに、非上場株式の株価算定には、法的なトラブルを未然に防ぐための注意も必要です。特に株主間や取引相手との合意形成は、評価額に対する不満や紛争の原因となり得ます。事前に評価方法や基準について合意を形成し、書面に残しておくことがトラブル回避につながります。
最後に、非上場株式の株価算定は、企業の将来に大きな影響を与える重要なプロセスです。客観的かつ公正な評価を心掛け、必要に応じて専門家の意見を取り入れることで、適切な判断を下すことができるでしょう。株価算定における注意点を押さえ、健全な企業運営に役立ててください。